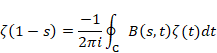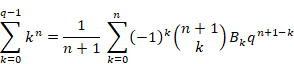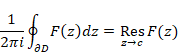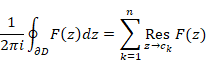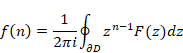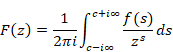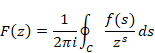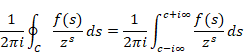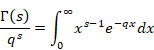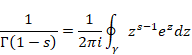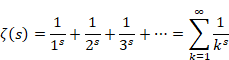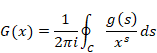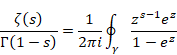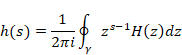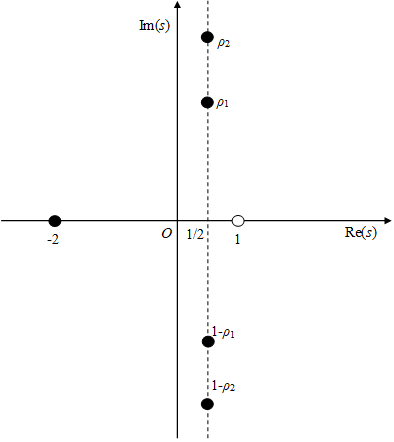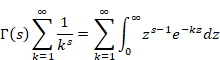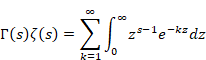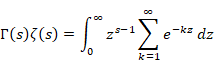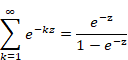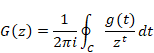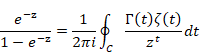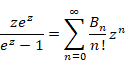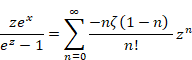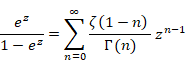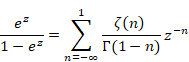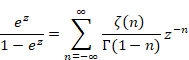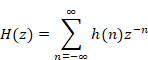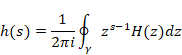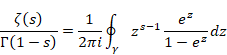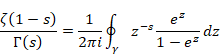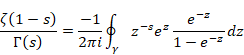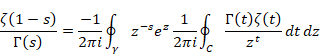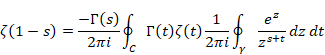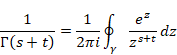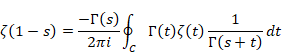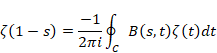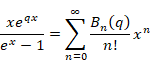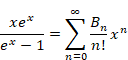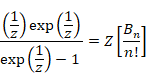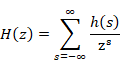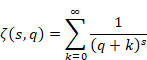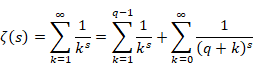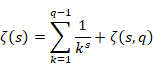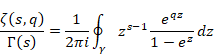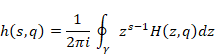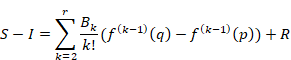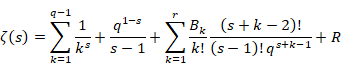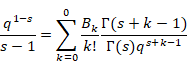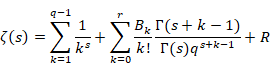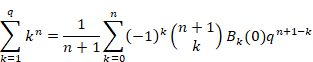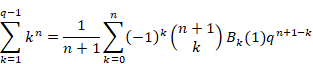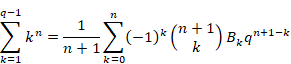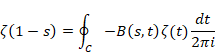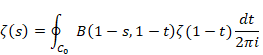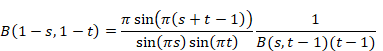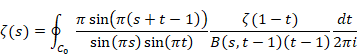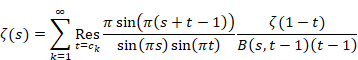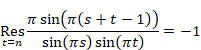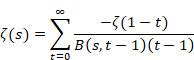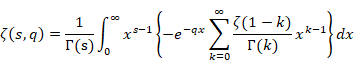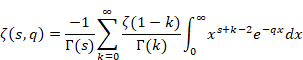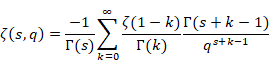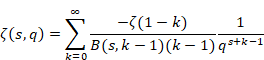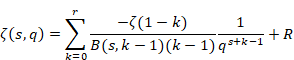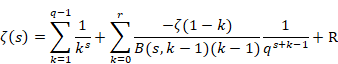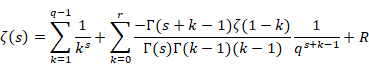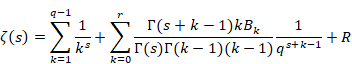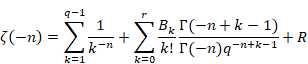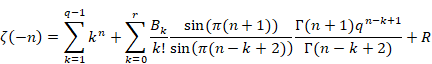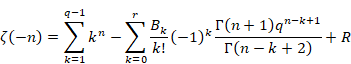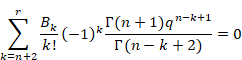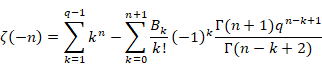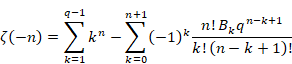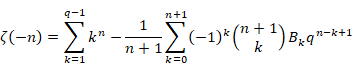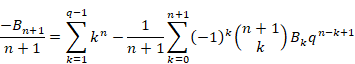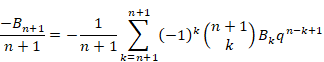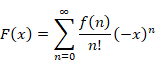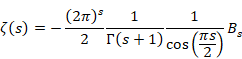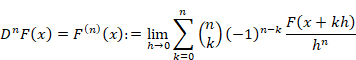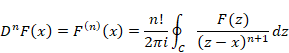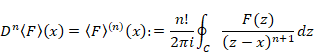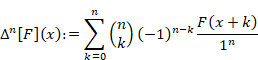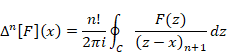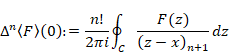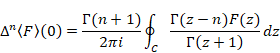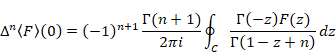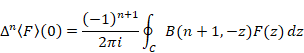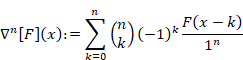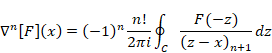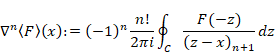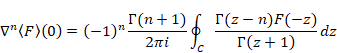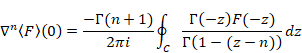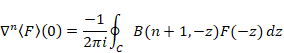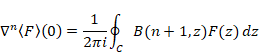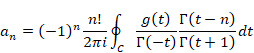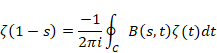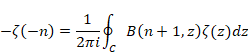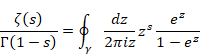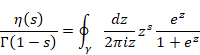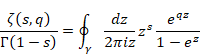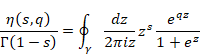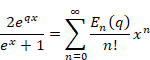複素解析によるゼータ関数の反射積分方程式の導出
ホーム > 量子力学 > ゼータ関数とベルヌーイ数
2019/04/07
公開日 2013/9/15
K. Sugiyama[1]
本論文では、逆メリン変換でゼータ関数の反射積分方程式を導出する。
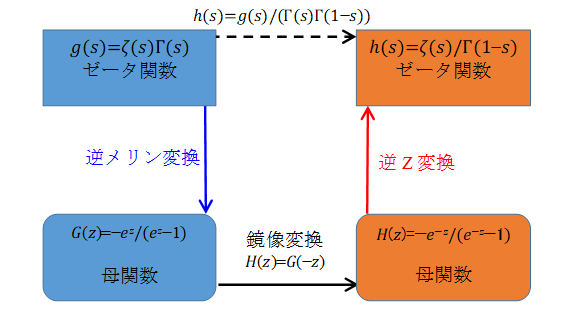
エラー! 参照元が見つかりません。
多くの研究者が、リーマン予想の証明を試みてきたが、成功していない。このリーマン予想の証明は数学の重要な課題となっている。本論文では、リーマン予想を証明する準備として、複素解析で反射積分方程式の導出を試みる。
逆メリン変換より、ある母関数を得る。その母関数を指数倍し、その符号を反転することで、新しい母関数を得る。その母関数を逆Z変換し反射積分方程式を導出する。
反射積分方程式から、ファウルハーバーの公式を導出する。ゼータ関数のn階後退差分がゼータ関数ζ (n)となることを示す。
目次
7 補足2: ゼータ関数の平均後退差分によるゼータ関数の表現
1 序論
1.1 課題
多くの研究者が、リーマン予想の証明を試みてきたが、成功していない。このリーマン予想の証明は数学の重要な課題となっている。本論文では、リーマン予想を証明する準備として、複素解析で反射積分方程式の導出を試みる。
1.2 課題の重要性
リーマン予想の証明は、数学における最も重要な未解決問題の一つである。
このため、多くの数学者がリーマン予想の証明を試みてきた。しかし、それらの試みは成功していない。リーマン予想を証明する方法の一つは、ゼータ関数の零点を、ある作用素の固有値と解釈することである。しかし、これまで、その作用素は見つかっていなかった。反射積分方程式は、この作用素のひとつと考えられる。このため、反射積分方程式の導出は重要な課題である。
1.3 これまでの研究動向
レオンハルト・オイラーは、1737年にゼータ関数の無限級数を導入した。ベルンハルト・リーマンは、1859年にゼータ関数の解析接続を導入した。
ダフィット・ヒルベルトとゲオルグ・ポリア[2]は1914年頃に、ゼータ関数の零点は、ある作用素の固有値であろうと予想した。この予想はヒルベルト=ポリア予想と呼ばれている。
ゼエフ・ルドニックとピーター・サルナック[3]は1996年にランダム行列理論で零点の分布を研究している。黒川重信氏は1996年頃より1元体[4]を研究している。アラン・コンヌ[5]は1998年に非可換幾何学とリーマン予想の関係を示した。クリストファー・デニンガー[6]は1998年に零点の固有値解釈を研究している。
1.4 本論文の新しい導出方法
逆メリン変換より、ある母関数を得る。その母関数を指数倍し、その符号を反転することで、新しい母関数を得る。その母関数を逆Z変換し反射積分方程式を導出する。
(反射積分方程式)
|
|
(1.1) |
反射積分方程式から、ファウルハーバーの公式とネールント=ライス積分を導出する。
(ファウルハーバーの公式)
|
|
(1.2) |
2 既知の内容の確認
本章では、既知の内容を確認する。
2.1 コーシーの留数定理
オーギュスタン=ルイ・コーシーは、1831年に留数定理[7]を発表した。
関数F (z)は単純閉曲線∂Dの内部の領域Dに孤立特異点cを持つほかは、領域Dの内部と周∂Dをこめて正則とする。このとき次の等式が成立する。
(留数定理)
|
|
(2.1) |
関数F(z)が孤立特異点ckを持つ場合は、次の等式が成立する。
(留数定理)
|
|
(2.2) |
2.2 フレビッツのZ変換
ビトルド・フレビッツ[8]は1947年にZ変換を発表した。関数F(z)が領域D = {0<|z|<R}で正則ならば、その領域内で広義一様収束する級数に変換できる。
(Z変換)
|
|
(2.3) |
|
|
(2.4) |
|
|
(2.5) |
したがって、原点Oと極iRの最小距離がRのとき、Z変換の領域Dは次のとおり。白丸は極である。
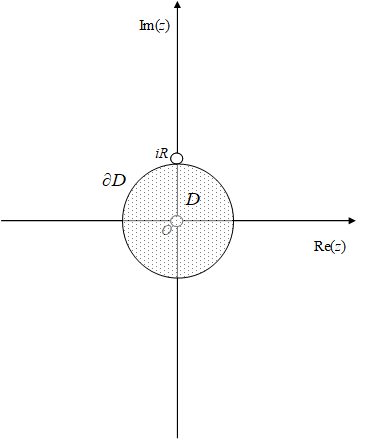
図 2-1: Z変換の領域
逆Z変換は、その領域Dを囲む積分経路∂Dの周回積分となる。
(逆Z変換)
|
|
(2.6) |
|
|
(2.7) |
2.3 メリン変換
ハジャルマー・メリン[9]は、1904年にメリン変換を発表した。
(メリン変換)
|
|
(2.8) |
|
|
(2.9) |
関数 f (s) が複素帯領域 S = {a < Re(s) < b} で正則で、 a と b の間にある任意の実数 c に対し Im(s) → ±∞ において f (s) → 0 ならば、次の線積分は絶対収束する。
(逆メリン変換)
|
|
(2.10) |
|
|
(2.11) |
|
|
(2.12) |
複素帯領域 S の実部は、被積分関数のすべての極の実部より大きい必要がある。複素帯領域 S を次の図に示す。白丸は極である。
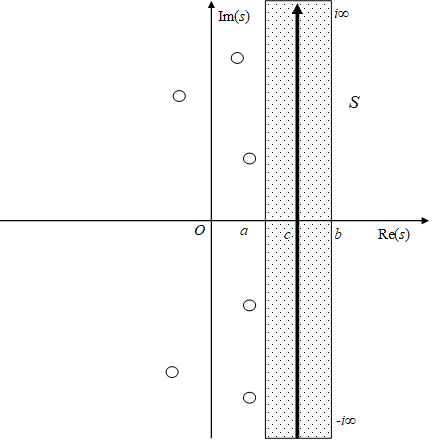
図 2-2: 逆メリン変換の複素帯領域S
逆メリン変換を周回積分で次のように定義する。
(逆メリン変換)
|
|
(2.13) |
|
|
(2.14) |
積分経路Cは被積分関数のすべての極を囲む経路とする。例として積分経路 C = CI + CRを次のようにとる。白丸は極である。
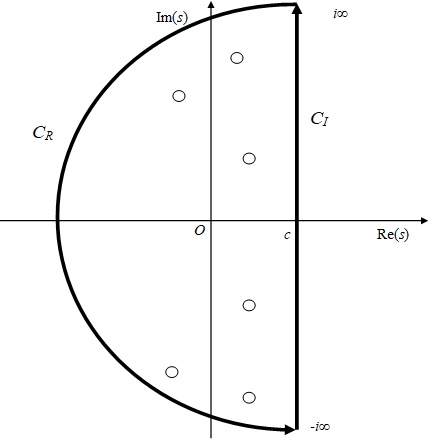
図 2-3: 逆メリン変換
積分経路CRの線積分が0ならば、積分経路Cの周回積分は積分経路CIの線積分に一致する。そのとき、次の式が成立する。
|
|
(2.15) |
2.4 オイラーのガンマ関数
レオンハルト・オイラー[10]は1729年に階乗の一般化としてガンマ関数を導入した。
(ガンマ関数)
|
|
(2.16) |
変数xを(qx)に置き換え、次の公式を得る。
|
|
(2.17) |
上記の式で(dx)は(qdx)に置き換えた。
ヘルマン・ハンケルは1863年に次の積分表示[11]を発表した。
(ガンマ関数の周回積分)
|
|
(2.18) |
ガンマ関数の積分経路は次の図の経路γである。
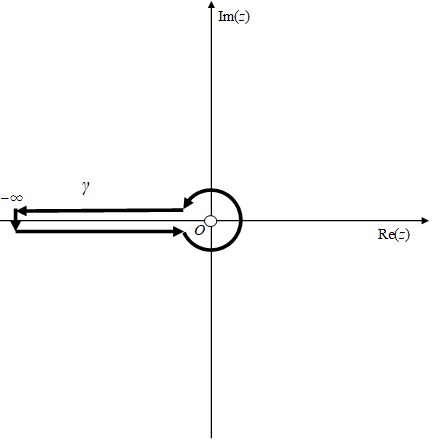
図 2-4: ガンマ関数の積分経路
ガンマ関数は次の公式を持つ。
(ガンマ関数の反射公式)
|
|
(2.19) |
上記の式は、オイラーの反射公式、相半公式、相反公式、相補公式とも呼ばれている。
2.5 オイラーのベータ関数
レオンハルト・オイラーは、1768年に彼の著書[12]でベータ関数を導入した。
(ベータ関数)
|
|
(2.20) |
ガンマ関数の反射公式により、ベータ関数の反射公式を得る。
(ベータ関数の反射公式)
|
|
(2.21) |
2.6 リーマンのゼータ関数
レオンハルト・オイラーは、1737年にゼータ関数の無限級数を導入した。
(ゼータ関数)
|
|
(2.22) |
ベルンハルト・リーマン[13]は、1859年にゼータ関数をガンマ関数で表現した。
(ゼータ関数)
|
|
(2.23) |
上記の式を次のメリン変換と解釈する。
(ゼータ関数のメリン変換)
|
|
(2.24) |
|
|
(2.25) |
|
|
(2.26) |
|
|
(2.27) |
その関数の逆メリン変換は次のとおりである。
(ゼータ関数の逆メリン変換)
|
|
(2.28) |
|
|
(2.29) |
|
|
(2.30) |
|
|
(2.31) |
ベルンハルト・リーマンは、1859年にゼータ関数の解析接続を導入した。
(ゼータ関数の解析接続)
|
|
(2.32) |
上記の式を、式(2.7)のような逆Z変換と解釈する。
(ゼータ関数の逆Z変換)
|
|
(2.33) |
|
|
(2.34) |
|
|
(2.35) |
|
|
(2.36) |
積分経路γを次の図に示す。白丸は極を意味する。
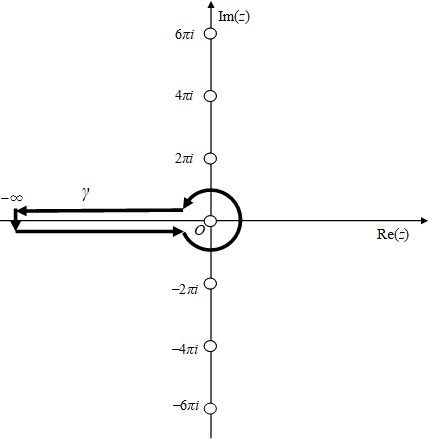
ゼータ関数のZ変換は次のとおり。
(Z変換)
|
|
(2.37) |
|
|
(2.38) |
|
|
(2.39) |
|
|
(2.40) |
メリン変換とZ変換の母関数は次の関係を持つ。
|
|
(2.41) |
|
|
(2.42) |
リーマンは次の公式を示した。
(リーマンの反射公式)
|
|
(2.43) |
リーマンは1859年に次の予想を提唱した。
(リーマン予想)
非自明な零点の実数部はすべて1/2である。
自明でない零点ρ1とρ2の例を次の図に示す。黒丸が零点、白丸は極である。
図 2-6: ゼータ関数の自明でない零点
|
|
(2.44) |
|
|
(2.45) |
このリーマン予想の証明は、未解決であり、重要な課題となっている。
3 反射積分方程式の導出
本章では、次の積分方程式を証明する。
(ゼータ関数の積分方程式)
|
|
(3.1) |
証明
導出方法の枠組みは次のとおり。
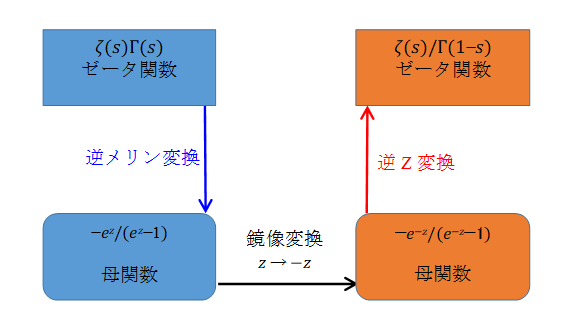
図 3-1: ゼータ関数の積分方程式導出の枠組み
一方、ガンマ関数は次の通り。
|
|
(3.2) |
変数zをkzに置き換え、dzをkdzに置き換える。
|
|
(3.3) |
両辺について、k = 1から無限大までの和を取る。
|
|
(3.4) |
左辺を次のゼータ関数で置き換える。
|
|
(3.5) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.6) |
右辺の和と積分の順序を入れ替える。
|
|
(3.7) |
ここで次の等比級数の公式を用いる。
|
|
(3.8) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.9) |
上記の式は次のようなメリン変換と解釈できる。
|
|
(3.10) |
したがって、次のような逆メリン変換が可能である。
|
|
(3.11) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.12) |
逆メリン変換では、積分経路Cは被積分関数のすべての極を囲む必要がある。そこで積分経路Cを次のように取る。白丸は極である。
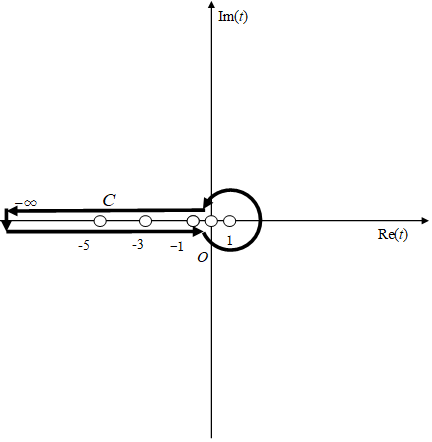
図 3-2: 逆メリン変換の積分経路
ここで、ベルヌーイ数は次の通り。
|
|
(3.13) |
一方、ゼータ関数とベルヌーイ数には次の関係がある。
|
|
(3.14) |
上記の式を式(3.13)に代入する。
|
|
(3.15) |
階乗をガンマ関数に置き換え、変形する。
|
|
(3.16) |
nを1−nに置き換える。
|
|
(3.17) |
2以上の自然数nに対し次の値は0になる。
|
|
(3.18) |
そのため、式(3.19)は次のように和を取る範囲を無限大まで延長できる。
|
|
(3.19) |
上記の式は次のようなZ変換と解釈できる。
|
|
(3.20) |
したがって、次のような逆Z変換が可能である。
|
|
(3.21) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.22) |
積分経路 γ は次の図のとおり。白丸は極を意味する。
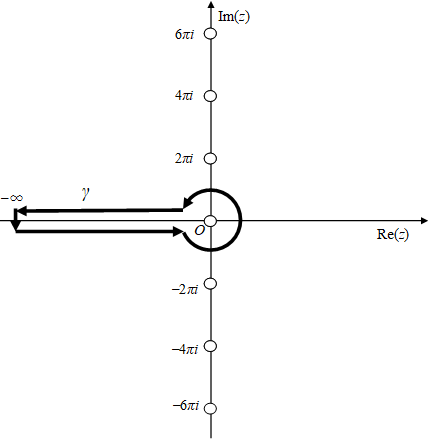
図 3-3: ゼータ関数の積分経路
sを1−sに置き換える。
|
|
(3.23) |
ここで次の式を用いる。
|
|
(3.24) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.25) |
上記の式に、次の式(3.12)を代入する。
|
|
(3.12) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.26) |
変形する。
|
|
(3.27) |
一方、ガンマ関数にはハンケルの積分表示がある。下記式を上記の式に代入する。
|
|
(3.28) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(3.29) |
次のベータ関数を使い、整理する。
|
|
(3.30) |
この結果、次の式を得る。
|
|
(3.31) |
上記が求めたい積分方程式だった。(証明終了)
∎
4 結論
本論文では、次の結果を得た。
・ゼータ関数の反射積分方程式を導出した。
5 今後の課題
今後の課題は次のとおり。
・ファウルハーバーの公式を導出する。
・ネールント=ライス積分を導出する。
・反射積分方程式の固有値を調べる。
6 補足1: ファウルハーバーの公式の導出
補足では、既知の内容を確認後、次の式を導出する。
・ファウルハーバーの公式
6.1 既知の内容の確認 (その2)
本節では、既知の内容を確認する。
6.1.1 ベルヌーイ多項式
ベルヌーイ多項式を次のように定義する。
(ベルヌーイ多項式)
|
|
(6.1) |
上記の級数は全領域で収束しない。原点と母関数の極の最小距離が2πのため、収束半径は2πである。
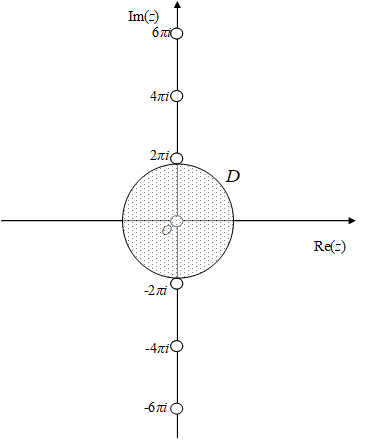
図 6-1: ベルヌーイ多項式の級数の収束半径
6.1.2 ベルヌーイ数
ヤコブ・ベルヌーイは1713年に彼の著書[14]で、ベルヌーイ数を導入した。
(ベルヌーイ数)
|
|
(6.2) |
正の偶数 n に対し、次の公式が成立する。
(ベルヌーイ数の反射公式)
|
|
(6.3) |
ヴィーフの著書[15]によれば、次のZ変換が存在する。
(ベルヌーイ数のZ変換)
|
|
(6.4) |
本論文では、次のZ変換を使用する。
(ベルヌーイ数のZ変換)
|
|
(6.5) |
|
|
(6.6) |
|
|
(6.7) |
|
|
(6.8) |
一方、ゼータ関数のZ変換は次の通り。
(ゼータ関数のZ変換)
|
|
(6.9) |
|
|
(6.10) |
|
|
(6.11) |
|
|
(6.12) |
したがって、次の式が成立する。
|
|
(6.13) |
変数sを負の整数-nに置換し、次の公式を得る。
(ベルヌーイ数の公式)
|
|
(6.14) |
従来、ベルヌーイ数は離散的であると考えられてきた。私は、ベルヌーイ数は連続的であると考える。連続的なベルヌーイ数をベルヌーイ関数と呼ぶ。私はベルヌーイ関数をゼータ関数の次のような異なる表現と解釈する。
|
|
(6.15) |
6.1.3 フルヴィッツのゼータ関数
アドルフ・フルヴィッツ[16]は1882年に、次のゼータ関数を導入した。
(フルヴィッツのゼータ関数)
|
|
(6.16) |
フルヴィッツのゼータ関数とリーマンのゼータ関数の関係を次に示す。
|
|
(6.17) |
|
|
(6.18) |
フルヴィッツのゼータ関数はq が1に等しいとき、リーマンのゼータ関数となる。
|
|
(6.19) |
フルヴィッツのゼータ関数をガンマ関数で表現する。
(フルヴィッツのゼータ関数)
|
|
(6.20) |
上記の式を次のメリン変換と解釈する。
(メリン変換)
|
|
(6.21) |
|
|
(6.22) |
|
|
(6.23) |
|
|
(6.24) |
フルヴィッツのゼータ関数の解析接続は次の通り。
(フルヴィッツのゼータ関数の解析接続)
|
|
(6.25) |
上記の式を、次の逆Z変換と解釈する。
(逆Z変換)
|
|
(6.26) |
|
|
(6.27) |
|
|
(6.28) |
|
|
(6.29) |
自然数nに対し、次の等式が成立する。
(ベルヌーイ多項式の公式)
|
|
(6.30) |
6.1.4 オイラー=マクローリンの和公式
オイラー[17]は1738年に次の公式を発見した。マクローリン[18]も1742年に、オイラーとは独立に同式を発見している。
(オイラー=マクローリンの和公式)
|
|
(6.31) |
|
|
(6.32) |
|
|
(6.33) |
上記の式において、変数Rは誤差項である。
6.1.5 漸近展開
オイラー[19]は1755年にオイラー=マクローリンの和公式でゼータ関数の値を計算している。
(ゼータ関数の漸近展開)
|
|
(6.34) |
上記の式において変数Rは誤差項である。導出方法の詳細は、エドワーズ[20]の1974年の著書にある。
ここで次の等式を用いる。
|
|
(6.35) |
その結果、次の式を得る。
(ゼータ関数の漸近展開)
|
|
(6.36) |
6.1.6 ファウルハーバーの公式
ヨハン・ファウルハーバー[21]は1631年にべき乗和の公式を提示した。自然数nに対し次の公式が成立する。
(ファウルハーバーの公式)
|
|
(6.37) |
上記の式をベルヌーイ多項式Bk(1)で表現する。
(ファウルハーバーの公式)
|
|
(6.38) |
本論文では、上記の式をベルヌーイ数Bkで次のように表現する。
(ファウルハーバーの公式)
|
|
(6.39) |
6.2 ファウルハーバーの公式の導出
ファウルハーバーの公式を導出するため、次の公式を導出する。
- リーマンのゼータ関数の総和方程式
- フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式
- リーマンのゼータ関数の漸近展開
6.2.1 リーマンのゼータ関数の総和方程式の導出
リーマンのゼータ関数の総和方程式を導出する。
反射積分方程式は次のとおり。
(反射積分方程式)
|
|
(6.40) |
上記の式において、変数 s を (1-s) に置き換え、変数 t を (1-t) に置き換える。
(反射積分方程式)
|
|
(6.41) |
積分経路 C0 を次の図に示す。白丸は極である。
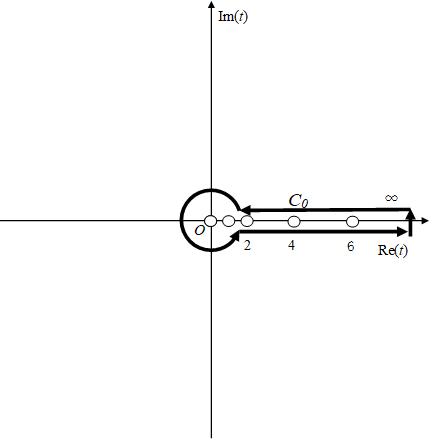
図 6-2:反射積分方程式の積分経路
上記の式に次の式を代入する。
(ベータ関数の反射公式)
|
|
(6.42) |
その結果、次の式を得る。
|
|
(6.43) |
上記の式を留数定理で積分する。
|
|
(6.44) |
ここで、 ck は k 番目の特異点である。特異点は 0, 1, 2, 4, 6, … である。
整数 n に対し次の等式が成り立つ。
|
|
(6.45) |
すべての特異点は整数であり、ゼータ関数 ζ (1-t) の値は t = 3, 5, 7, … で零であるため、次のように書ける。
(総和方程式)
|
|
(6.46) |
上記の式は発散するため、計算できない。この問題を解決するため、次の節で、フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式を導出する。
6.2.2 フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式の導出
この節では、フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式を導出する。
フルヴィッツのゼータ関数は次の通り。
(フルヴィッツのゼータ関数)
|
|
(6.47) |
上記の式をメリン変換の母関数で次のように表現する。
|
|
(6.48) |
上記の式は次のように変形できる。
|
|
(6.49) |
上記の式の関数H(x)にゼータ関数のZ変換を代入すると下記となる。
|
|
(6.50) |
|
|
(6.51) |
そのZ変換は領域Dで収束する。したがって、その領域で、積分と総和の順序を変更できる。
変数 x について積分するため、次のように式を整理する。
|
|
(6.52) |
この式に、次のガンマ関数の等式(2.17)を適用する。
|
|
(6.53) |
その結果、次の式が得られる。
|
|
(6.54) |
ここで、次のベータ関数(2.20)を利用して式を簡略化する。
|
|
(6.55) |
すると下記式となる。
(フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式)
|
|
(6.56) |
「ベルヌーイ関数の級数定義式」は収束半径が2πのため、上記の式は発散する。そのため、総和の上限値を変数qに依存する変数rに変更する。
(フルヴィッツのゼータ関数の総和方程式)
|
|
(6.57) |
ここでRは誤差項である。
6.2.3 漸近展開の導出
本節ではゼータ関数の漸近展開(6.36)を導出する。
リーマンとフルヴィッツのゼータ関数の関係は次の通り。
|
|
(6.58) |
したがって、リーマンのゼータ関数の総和方程式は次のように表現できる。
(総和方程式)
|
|
(6.59) |
ベータ関数をガンマ関数に置き換えると下記式を得る。
|
|
(6.60) |
ベルヌーイ多項式の等式により次のように変形する。
|
|
(6.61) |
上記の式を変形し、ゼータ関数の漸近展開を得る。
(ゼータ関数の漸近展開)
|
|
(6.62) |
6.2.4 ファウルハーバーの公式の導出
本節ではファウルハーバーの公式を導出する。
ゼータ関数の漸近展開(6.36)は次の通り。
(ゼータ関数の漸近展開)
|
|
(6.63) |
上記の式において、変数sを(-n)に置き換える。
|
|
(6.64) |
上記の式に、オイラーの反射公式を適用し次の式を得る。
|
|
(6.65) |
整数kに対し次の等式が成り立つ。
|
|
(6.66) |
したがって、次の式を得る。
|
|
(6.67) |
自然数n、整数k > n+1に対し次の式が成立する。
|
|
(6.68) |
したがって、次の式が成立する。
|
|
(6.69) |
k > n+1の項の値がすべてゼロであるため、誤差項Rを消し、式(6.67)の総和の上限をn+1に変更する。
|
|
(6.70) |
上記の式を階乗記号で次のように表現する。
|
|
(6.71) |
二項係数で次のように表現する。
|
|
(6.72) |
ベルヌーイ多項式の等式により次のように変形する。
|
|
(6.73) |
自然数n、整数k = n+1に対し次の式が成立する。
|
|
(6.74) |
その結果、次の式が成立する。
|
|
(6.75) |
したがって、式(6.73)を次のように変形し、ファウルハーバーの公式を得る。
(ファウルハーバーの公式)
|
|
(6.76) |
上記の式が、本節で導出したい式であった。
7 補足2: ゼータ関数の平均後退差分によるゼータ関数の表現
7.1 既知の内容の確認(その3)
本節では、既知の内容を確認する。
7.1.1 ラマヌジャンの主定理
シュリニヴァーサ・ラマヌジャンは1910年ごろに実数xと複素数sに対し次の定理を得た[22]。
(ラマヌジャンの主定理)
|
|
(7.1) |
|
|
(7.2) |
上記の式は次のベルヌーイ数とゼータ関数で成立する。
|
|
(7.3) |
|
|
(7.4) |
|
|
(7.5) |
この定理は次の関係式を示唆している。
|
|
(7.6) |
7.1.2 ウーンの連続的なベルヌーイ数
ウーン[23]は1997年に、連続的なベルヌーイ数を導入した。
自然数nに対し、次の公式が成立する。
(ベルヌーイ数の公式)
|
|
(7.7) |
ウーンは複素数sに対し次の等式を提案した。
(ベルヌーイ関数の等式)
|
|
(7.8) |
本論文では、ベルヌーイ数の従来の表記法に基づき、ベルヌーイ関数に対し次の表記法を用いる。
(ベルヌーイ関数の等式)
|
|
(7.9) |
上記の式をリーマンの反射公式に代入し、次の式を得る。
|
|
(7.10) |
上記の式を変形することで次の式を得る。
(ベルヌーイ関数の反射公式)
|
|
(7.11) |
上記の式は正の偶数 s に対し、下記式となる。
|
|
(7.12) |
上記の式は、正の偶数 n に対する次の式と等しい。
(ベルヌーイ数の反射公式)
|
|
(7.13) |
上記の結果は、ベルヌーイ関数の等式の妥当性を示唆する。
7.1.3 コーシーの積分公式
微分は次のように定義される。
|
|
(7‑14) |
2階微分は次のように定義される。
|
|
(7‑15) |
n階微分は次のように定義される。
|
|
(7‑16) |
ここで、![]() は二項係数である。
は二項係数である。
|
|
(7‑17) |
関数F(z)が経路C内で正則の場合、n階微分はコーシーの積分公式で表現できる。
(コーシーの積分公式)
|
|
(7‑18) |
関数F(z)が経路C内で正則でない場合、n階微分はコーシーの積分公式で表現できない。関数F(z)を経路Cで平均した関数f(z)の微分が得られる。平均化した微分であるため、新しい記号![]() で表現する。
で表現する。
(コーシーの平均微分公式)
|
|
(7‑19) |
7.1.4 ネールント=ライス積分
前進差分は次のように定義される。
|
|
(7‑20) |
2階前進差分は次のように定義される。
|
|
(7‑21) |
n階前進差分は次のように定義される。
|
|
(7‑22) |
正則の場合、n階前進差分はネールント=ライス積分で表現できる。
(ネールント=ライス積分)
|
|
(7‑23) |
ここで (z−x)n+1は下降階乗である。
|
|
(7‑24) |
ネールント=ライス積分はニールス・エリク・ネールントが1924年にを発表した[24]。
関数F(z)が経路C内で正則でない場合、n階前進差分はネールント=ライス積分(7‑23)で表現できない。関数F(z)を経路Cで平均した関数の差分が得られる。平均化した前進差分であるため、新しい記号![]() で表現する。
で表現する。
(ネールント=ライス平均前進差分公式)
|
|
(7‑25) |
x=0とし、階乗と下降階乗をガンマ関数で表現する。
|
|
(7‑26) |
ガンマ関数の反射公式より次の式が成り立つ。
したがって式(7‑27)を式(7‑28)で割ることにより、次の式が成り立つ。
|
|
(7‑29) |
ここで、次の式が成り立つ。
|
|
(7‑30) |
したがって、式(7‑29)は次のようになる。
|
|
(7‑31) |
したがって、式(7‑26)は次のようになる。
|
|
(7‑32) |
ガンマ関数をベータ関数で表現する。
(ネールント=ライス平均前進差分公式)
|
|
(7‑33) |
7.1.5 ネールント=ライス積分(後退差分)
後退差分は次のように定義される。
|
|
(7‑34) |
2階後退差分は次のように定義される。
|
|
(7‑35) |
n階後退差分は次のように定義される。
|
|
(7‑36) |
関数F(z)が経路C内で正則の場合、n階後退差分はネールント=ライス積分で表現できる。
(ネールント=ライス積分)
|
|
(7‑37) |
ここで (z−x)n+1は下降階乗である。
|
|
(7‑38) |
関数F(z)が経路C内で正則でない場合、n階後退差分はネールント=ライス積分(7‑37)で表現できない。関数F(z)を経路Cで平均した関数f(z)の差分が得られる。平均化した後退差分であるため、新しい記号![]() で表現する。
で表現する。
(ネールント=ライス平均後退差分公式)
|
|
(7‑39) |
ここでx=0とし階乗と下降階乗をガンマ関数で表現する。
|
|
(7‑40) |
ガンマ関数の反射公式より次の式が成り立つ。
したがって式(7‑41)を式(7‑42)で割ることにより、次の式が成り立つ。
|
|
(7‑43) |
ここで、次の式が成り立つ。
|
|
(7‑44) |
したがって、式(7‑43)はつぎのようになる。
|
|
(7‑45) |
したがって、式(7‑40)はつぎのようになる。
|
|
(7‑46) |
ガンマ関数をベータ関数で表現する。
(ネールント=ライス平均後退差分公式)
|
|
(7‑47) |
zを-zに置き換える。
(ネールント=ライス平均後退差分公式)
|
|
(7‑48) |
7.1.6 ポアソン=メリン=ニュートン循環
ネールント=ライス積分に関連し、フラジョレットは1985年にポアソン=メリン=ニュートン循環を発表した[25]。
(ポアソン=メリン=ニュートン循環)
|
|
(7.49) |
|
|
(7.50) |
|
|
(7.51) |
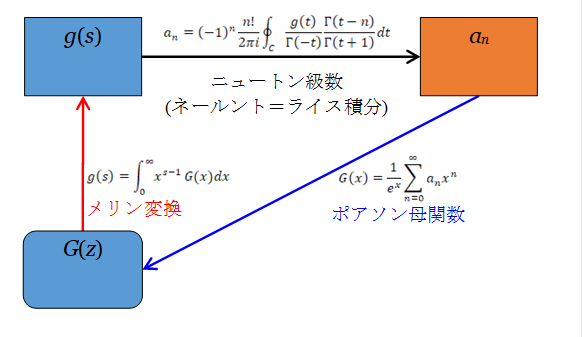
図 7-1: ポアソン=メリン=ニュートン循環
7.2 ゼータ関数の平均後退差分によるゼータ関数の表現
ゼータ関数の平均後退差分はゼータ関数と等しい。
|
|
(7‑52) |
証明
ゼータ関数の反射積分方程式より下記が成立する。
|
|
(7‑53) |
両辺に-1をかけ、複素数1-sを-nとする。
|
|
(7‑54) |
上記の式(7‑54)の右辺をネールント=ライス平均後退差分公式(7‑48)の右辺と比較し次の式を得る。
|
|
(7‑55) |
上記が求めたい式であった。(証明終了)
■
ゼータ関数では平均後退差分は、通常の後退差分で次のように表現できる。
|
|
(7‑56) |
ネールント=ライス積分は前進差分でも定義可能だが、前進差分では上記のようにゼータ関数を簡潔に表現できない。計算過程を省略し結果だけを記すと下記となる。
|
|
(7‑57) |
|
|
(7‑58) |
ここで、![]() は平均前進差分であり、
は平均前進差分であり、![]() は通常の前進差分である。
は通常の前進差分である。
8 付録
8.1 逆Z変換表
逆Z変換表は次のとおり。
表 8‑1:逆Z変換表
|
# |
|
|
番号 |
|
1 |
|
|
(8.1) |
|
2 |
|
|
(8.2) |
|
3 |
|
|
(8.3) |
|
4 |
|
|
(8.4) |
上記の関数は次のとおり。
(リーマンのゼータ関数)
|
|
(8.5) |
(ディリクレ[26]のイータ関数)
|
|
(8.6) |
(フルヴィッツのゼータ関数)
|
|
(8.7) |
(フルヴィッツのイータ関数)
|
|
(8.8) |
多項式の公式は次のとおり。
|
|
(8.9) |
|
|
(8.10) |
|
|
(8.11) |
|
|
(8.12) |
|
|
|
多項式の定義は次のとおり。
(ベルヌーイ多項式)
|
|
(8.13) |
(オイラー多項式)
|
|
(8.14) |